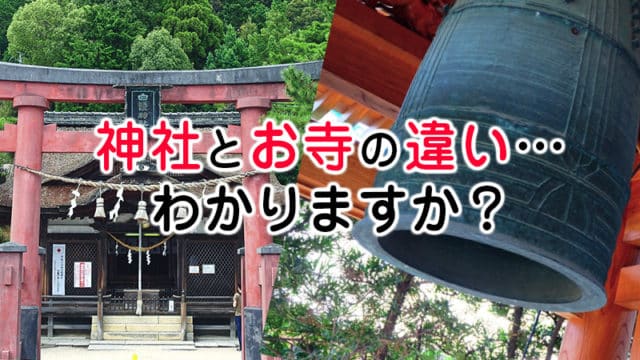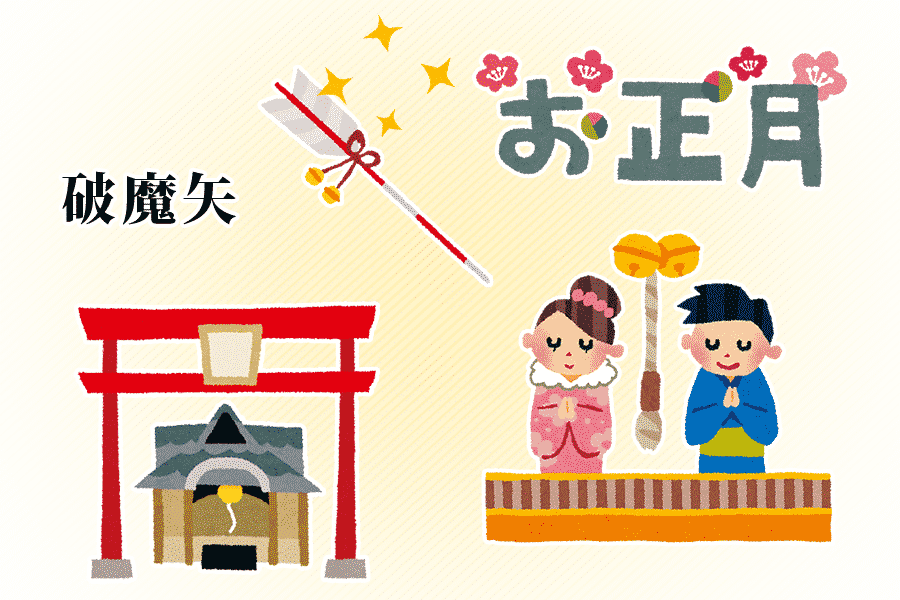お正月らしい行事のひとつといえば、初詣ですね。
新年を改まった気持ちで迎えるためにも、わたしも神社に毎年お参りに行きますが
例えば家族と神社に行って初詣を済ませてあるのに、さらに会社のおつきあいでお寺に参拝にいくことになったら・・どうなるのでしょうか。
とくに信心深くなくても、新年早々うっかりバチあたりなことをして悪運を呼び込んでも・・・と不安になりませんか?
目次
初詣で神社とお寺、両方お参りしても大丈夫?
安心してください。初詣で神社とお寺の両方に参拝に行っても、何の問題もないようです。
というのも、もともと日本では神道と仏教の区別がされていなかったという歴史的事実があったんです。
仏教は日本に5-6世紀ごろ大陸から伝わってきたといわれていますが、それのもっと以前より日本には自然の物に神が宿るとする神道があって、仏教が入ってきたあと、両方が並存という道をたどりました。
それが江戸時代終わりまで続きました。日本はもともと神仏混合だったということです。
明治時代になってから、神仏分離令により神社と寺が分けられました。
ということで、初詣に神社に行ってその足ですぐお寺に参拝に行っても、何の問題もない、というわけです。
同じ部屋に神棚と仏壇が置いてある家も多いと思いますが、そういう訳なのですね。
初詣で神社とお寺にお参り。意味やご利益の違いは?
初詣の本来の意味は、【新しい年を迎えるにあたって、今年の目標や決断など自覚を促すため】
つまり自分自身の気持ちを引き締めるだとか、目標を新たにして、それを神様やご本尊さまに報告する、そんな意味合いがあるようです。
だから、初詣にいく場合には、どこの神社やお寺でも同じ目的を果たせるわけですが、
それでも祈願や厄払いといったことでは、個別の神社仏閣にはいわば「得意分野」というものもありますので、何か目的がある場合には、やはり下調べして選んだほうがいいですね。
例えば、稲荷神社では商売繁盛
○○八幡宮 や ○○神宮では
色々何でも叶えてくれる
○○明神
縁結びや商売繁盛の神様
などです。
またお寺でも、交通安全、家内安全、商売繁盛、合格祈願などなど、いろいろなお願いを聞いてくれますが、特に交通安全で有名、合格祈願で有名、といった専門がありますね。
どの神社やお寺に行くのが一番縁起がいいか、ということで決めるなら、恵方で選んでもいいかも知れません。
恵方とは、陰陽道でその年の福徳を司る神である「歳徳神」のいる方位で、かつては、初詣は自宅から見て恵方の方角の寺社に参る習慣があったそうですよ。
でも現代は方位にこだわる人はほとんどいないのでは?
基本的になじみがある近所の神社や仏閣、または新年らしい雰囲気を楽しむためだったら、人が多く訪れる有名な神社やお寺、という基準でいいのではないかと思います。
初詣の参拝作法について
神社とお寺では参拝のお作法が違います。ここではそれぞれの作法について、まとめましたので、参拝に行く前に是非復習しておきましょう。
神社での参拝作法
鳥居をくぐる前に会釈 →気持ちを引き締めてから境内に入る
手水舎(御手洗)の水で心身を清める
→右手で柄杓をもち、左手を清める
→左手にもちかえ、右手を清める
→右手にもちかえ、左手のひらに水を受けて口をすすぐ
→口をすすぎ終えたら水を左手に流す
→水の入った柄杓を立てて、柄に水を流してから伏せておく
御手洗がなかったり水が涸れていて使えない場合は省略
参道を通りご神前へ →参道の真ん中は神様の通り道とされているので避けて通る
賽銭箱の前で会釈
お賽銭を入れる→神様に対する真心のしるし
お賽銭の額にご利益の違いはないそうです
鈴を静かに一回鳴らす
二礼二拍手一礼
→深いお辞儀を二回
→拍手を二回
→両手を合わせてお祈り
→両手をおろし、深いお辞儀一回
願をかける場合は、はじめてその神社を訪れるときは、自分の名前を住所を神様に伝えてから、感謝しつつお願いごとを伝える
帰りの際、鳥居をくぐってから鳥居に向かい再度一礼
お寺の参拝方法
寺院の入り口にある山門で合掌一礼
お寺の参道は真ん中を歩いても構わない
特に敷石がある場合は参道を歩かずに敷石の上を歩くのはマナー違反
御手洗で身を清める。手順は神社参拝と同じ
鐘をつける場合はつく。(禁止しているお寺もありますから、ついてもよいか確認してからにしましょう)
蝋燭やお線香が用意されている場合は、料金(志納金)を支払って購入
火をつけて燭台と香炉に捧げる
蝋燭は一本、線香は三本、もしくは一本
本堂に礼拝
お賽銭を収め、鈴があれば鳴らす
神社へのお賽銭は「日頃の感謝を込めた供物」ですが、お寺へのお賽銭は「自分の欲を捨てるためのお布施」の意味があるそうです。
捧げ物の意味合いが強い神社に対して、寺院へのお賽銭は修行の一つなのですね。
姿勢を正し、静かに合掌して一礼。45度から90度に屈める。
数珠を持っている場合は、この時に手にかけておく
拍手は行わないこと
最後一礼
山門から出る際に、本堂に向かって合掌一礼
おみくじ、お守り、破魔矢について
おみくじや、お守り、それから破魔矢をいただくのは参拝後です。
1年間お守りいただいたあと、来年の初詣でお返する、というのが基本のようです。
(ただし合格祈願や安産祈願のお守りは結果が現れたらお返しするものだそうです)
神社のお守りは神社へ。寺院のお守りは寺院に返しましょう。
神社でいただいたものは、どうしても同じ神社に行けない場合は、他の神社に持って行くこともできるようです。
その他の作法
参道を歩いている時に神職や僧侶の方とすれ違ったときには、神職や僧侶の方に道を譲り、自分たちは脇に寄り頭を下げて通り過ぎるのを待つのが作法だそうです。
まとめ
神社とお寺が「一緒」という結論は筆者もびっくりしましたが、なんとなく行っていた初詣にもいろいろな意味があったことが分かり、今年からまた新たな気持ちでお参りができそうです。
お正月関連記事
お正月の破魔矢の飾り方。破魔矢の意味や返納方法は?